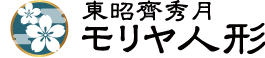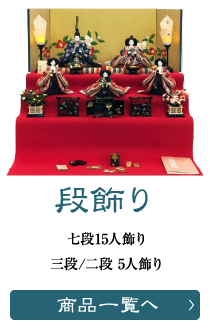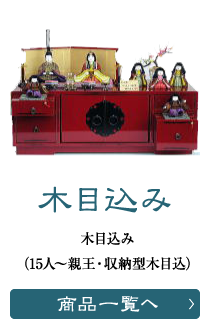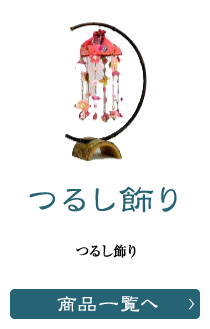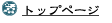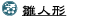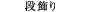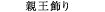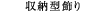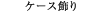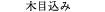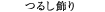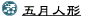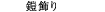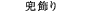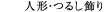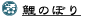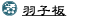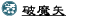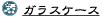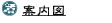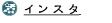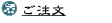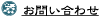| 女の子のすこやかな成長を祈る雛祭り(ひなまつり)。 明治創業以来100余年あまりの経験をもとに心を込めて作られる雛人形。東昭齊秀月モリヤが厳選し製作監製した気品高い面差しと優雅な衣装の雛人形をぜひご覧になってください。 当店の特長としましては衣装、頭(かしら)からお道具まで高品質のものだけを厳選し、またお客様の声を多数取り入れ納得していただけるもののみを販売していることです。 段飾り・親王平飾り・収納型飾り・ケース飾り・木目込み飾り・その他(つるし飾り)・名前旗 の商品を展示・販売しております。 |
 |
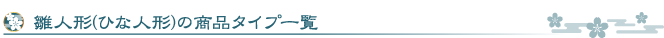

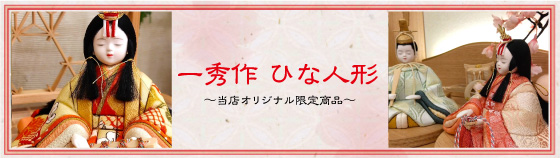

|
雛人形のセミオーダーが可能
ご予算、お好みに合わせて道具類(前飾り・雪洞・お花)の組み換えが一部可能です。また道具類(前飾り・雪洞・お花)の単品のみでもお買い上げいただけます。 ※一部できないセットもございますのでお問合せ下さい。 記念すべき雛人形をお選びいただく時に満足いただけるよう当店一同努力させていただきますので、お気軽にご相談下さい。 雛人形(ひな人形)の種類
東昭齊秀月モリヤで展示・販売しております雛人形(ひな人形)の種類としましては、三段5人飾り・二段5人飾り、親王飾り・立雛飾り、ケース飾り、収納型飾り、木目込飾りなど、専門店ならではの専門店にしかないお品揃えをしております。素材としましては、正絹衣装・ゴブラン織り・金彩刺繍・蘇州刺繍など極上のものばかりです。 また全てのお人形に当店で厳選した上品なお顔の頭(かしら)をお付けしております。 人形以外の台なども高品質な杉や桐を使用し、屏風は画家による手描きのものや生のお花を使用した「押花屏風」ををご用意しました。お道具類もひとつひとつこだわりをもってお人形に合わせております。 雛人形(ひな人形)の選び方【大きさ】
全国的に有名な桃の節句の雛人形は近年だいぶ小型化してまいりました。まず雛人形の種類ですが、雛人形は大きく分けて衣装着と木目込みとございます。簡単にいいますと衣装着とは衣装を着せており、木目込みとは衣装を張って造っております。通常の雛人形は衣装着とされており、衣装着のほうが断然豪華でございます。木目込みは可愛らしく飾る手間と場所をとらないのが利点です。木目込みといいますと昔は趣味やお二人目のお子様に趣向を変えて買われたかたが多いようです。ただ最近では木目込みを雛人形のメインとされるかたが増えてまいりました。木目込み人形でも充分お飾りいただける楽しみはございますので、住宅事情やお考え方次第では木目込みを雛人形のメインとして飾られても良いかと思います。 衣装着タイプとしましては昔はあたりまえのように飾られていた七段15人飾りがかなり減少しており、さらに三段5人飾りも少なくなってまいりました。 最近、最も需要が多いのは親王飾りです。親王飾りの良い点は奥行きをとらず、豪華なお殿様とお姫様をシンプルにお飾りいただけます。サイズとしましては大き過ぎず小さ過ぎずで幅(間口)55cm~65cmのものが人気です。またさらにコンパクトさを重視した収納型も人気です。収納時には1つの箱に収まるのが利点です。 (収納型のお人形より通常の親王飾りのお人形のほうが大きさや造りは豪華です。) 雛人形(ひな人形)の選び方【ケース】
その他ではケース飾り(アクリルケース・ガラスケース)がございます。雛人形の場合ケース飾りは人形が全てケース内に接着されているものがほとんどです。利点としてはホコリを被らず出し入れが簡単です。難点としてはお子様が雛人形に直接触れることができず飾る楽しみがないということです。アクリルケースとガラスケースとでも一長一短ございます。アクリルケースは軽くて割れないのが利点ですがキズが目立ちやすいため拭くことができません。逆にガラスケースはガラスですので割れる可能性はありますがキズが目立たず拭くことができるのが利点です。どのタイプが良いかはお客様のお考え方次第と住宅事情でございますが、もしお迷いのお客様には当店のアドバイスとしまして無理なく毎年飾っていただけるようにということと、ケースタイプよりはお客様が直接雛人形に触れていただきお飾りいただけるタイプ(ケース飾り以外)をおススメしております。大事なお子様のお節句として、お子様がお母さんと一緒に飾ったこと、飾れたことが良い思い出になるかと思います。お子様が2~3才になったらお飾りもきっと楽しいと思います。多少の破損等もあるかとは思いますがそれもお子様との良い思い出としてご家族皆様でお飾りいただくことを楽しい思い出にして下さい。そういった意味でも雛人形のお飾りを大変・・と思うかお節句のイベントとして飾ることを楽しむかはお客様お考え方次第かと思います。 アフターケア
東昭齊秀月モリヤ人形店では、心をこめたお祝いの品である雛人形(ひな人形)を末永くお飾りいただきたいと願っております。そのため特に、保証、修理等のアフターケアも万全に対応させていただいております。当店では特に保証年数などは設けておりません。状況や状態にもよりますが、当店でご購入頂きました商品につきましてはなるべく料金のかからないよう修理させていただきます。料金のかかる修理の場合でもなるべくご負担が少なく済むように低価格でお直しさせていただきます。 |
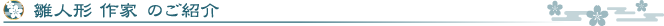
伝統工芸士 清水久遊


 |
節句を迎えるお子様には思いやり優しさに包まれ育つように願い、また大人様には伝統美、色彩美、 技巧美から醸し出される優雅で繊細なお雛様を手にしたときに満足感と安堵感をご提供できるよ う、また「ひいな」の創りだすお人形が皆様の生活の一部になれるよう日々切磋琢磨し、雛人形創 りに邁進してまいります。 |
| 清水久遊(しみずくゆう)プロフィール 1938年 愛知県蒲郡市生まれ 18歳より嫁ぎ先にて人形師の道を志す 1965年 雛人形工芸士に認定 1986年 有職工房「ひいな」を設立 1993年より東京高島屋において雛人形の制作実演を行う 2008年 NHK名古屋ホットイヴニング「東海の匠」取材放映2010年 朝日新聞社主催 日本の色目・重ね色 企画展in姫路 2011年「JAPANN EXPO日本文化フェスティバルInパリ」に出品 2012年「TBS Doll Show2nd」に出品 |
節句人形工芸士 田村芙紗彦


 |
最初は官女・五人囃子・左大臣・右大臣・仕丁の13種の人形士(着せ付け士)として開業。その後、三代目 望月和人が独学で姫・殿の製作に着手。研究を重ねた人形の形は、前から見ると、重心の低い正三角形で、高級感と安心感を醸し出す。斬新な配色と紋様をもちいつつ、伝統的な雰囲気を忘れないデザインセンスは全国でも高く評価されている。 |
| 田村芙紗彦(たむらふさひこ)という名前は、工房創設者である二代目が、趣味の小唄を披露する際に使用した芸名であり、これを拝借して名付けた。工房の創設者に敬意を表し、職人芸・芸能に通ずるように、という想いが込められている。 受賞歴 1995 通商産業大臣賞受賞『香のうつり』 1998 通商産業大臣賞受賞『四季の色重ね』 1999 文部大臣賞受賞『若紫』 2000 通商産業大臣賞受賞『源氏香』 |
節句人形工芸士 博暁


 |
伝統の有職故実をふまえ確かな時代考証のもとで作り出される作品は、見つめるほどに心を惹きつけ深い魅力を醸し出す また素材の美しさを充分に生かした、優美で高貴なその作風と洗練された独特の感性は高く評価されている。 平成28年「節句人形工芸士」の認定を受ける。 |
伝統工芸士 小野島久佳


 |
埼玉県鴻巣市に生まれる。 平成18年工房道翠に入り、女性初の埼玉県伝統工芸士である長島翠房並びに後継の飯嶋紫純に師事し雛人形の制作を始める。 |
| 令和元年、埼玉県より伝統工芸士に認定される。 一般的には男性の職人が多い中ではあるが、古式ゆかしい伝統をいかしつつも、女性 ならではの感性で雛人形の衣装にその時々に合った色調を取り入れ、柔らかな風合い をもつ曲線美を大切にした作風にこだわっている。 |
節句人形工芸士 柴田家千代 

 |
名古屋で生まれ、大学卒業とともに株式会社スキヨ人形研究所に入社。曾祖母はスキヨ人形創業者、祖母はフランス人形デザイナー、
二世柴田家千代は叔母にあたる。 |
| 二世柴田家千代を師とし、刺繍などの加工物、色合わせ、仕上げの技術などを身に着けていく。 日本人形の制作にも携わり、人形作りを学ぶ。 2019年には、柴田香瑚として、おぼこ立雛「心春(こはる)」を発表。 2024年柴田家千代を引き継ぎ、節句人形工芸士を取得。 二世が培ってきた「小さくてもよいものを」の気持ちを基本に、これからの世代のセンス・感覚を取り入れ、ひな人形飾りの世界を表現。 |
節句人形工芸士 優香 

 |
平初代は幾つもの人形工房を訪ね歩き、雛人形を取り巻く伝統芸術の世界を学びながら、独自に作風を作り上げた。その初代に師事し、雛人形作りをはじめた二代目優香は、郷土雛として知られる「箱雛」の産地である福岡県南部で生まれる。 |
| そこで生まれ育ったことで、幼い頃より雛人形に興味を抱き続けていた。 伝統の有識故実を十分ふまえ、日本独自の絵柄文様を織り込んだ素材の魅力を充分活かしたその作風は、初代から引き継いだ女性らしい優しさと洗練された感性により、春の宴に向かう自然の佇まいを感じさせている。 平成28年「節句人形工芸士」の認定を受ける。 |
伝統工芸士 鈴木晃隆


 |
鈴木 晃隆 (経済産業大臣認定 伝統工芸士) 幼少の頃より、現代の名工・鈴木柳蔵(初代晃隆)に師事。 |
| あらゆる日本人形頭を創造する頭師として、英才指導を受ける。 以後、鈴木晃隆を襲名し、日本人形の世界に技術革新を取り入れた多くの創作品を生み出し、岩槻人形の発展に大きく寄与。 眞子内親王殿下、佳子内親王殿下の雛人形を製作する等、その作品は皇室御用達品としても深く愛されている。 国の日本文化振興行事において、文化親善大使等を歴任し、世界各国へ日本人形の伝統文化を広める活動も行っている。 内閣総理大臣賞、経済産業大臣賞、文部科学大臣賞、厚生労働大臣賞、埼玉県知事賞、さいたま市長賞等、受賞歴多数。 |
伝統工芸士 柿沼 東光 

 |
昭和23年9月東京都荒川区生まれ。 昭和46年株式会社吉徳大光に師事。 昭和49年に伝統工芸士柿沼東光に師事し以来江戸木目込人形製作に専念。 華麗なる色彩による親王飾り、風俗人形などを発表。 |
| とりわけ螺鈿の象嵌や彩色二衣重の木目込み人形など独自の技法を学び、技術向上に努めながら、常に“時代の今”を見つめ、斬新な作品づくりに取り組むスタイルで新しい東光ブランドを築いている。 平成11年2月 通産大臣認定伝統工芸士 平成12年2月 東京都知事認定伝統工芸士 |
伝統工芸士 松崎幸一光


 |
大正9年創業。現三代目松崎幸一光は、昭和28年に東京で生まれ、昭和46年に18歳で父である先代、松崎幸雄(二代目 昭玉)に師事。昭和63年には京都府立文化博物館に平治物語絵巻の信西の巻を基に武者行列を製作。 |
| 平成17年には数々の功績が認められ、東京都知事認定 東京マイスターに選ばれる。 現在に至るまで、総理大臣賞4回、通産大臣賞4回を始め数々の受賞歴を有し、江戸木目込界を代表する作家の一人。 |
伝統工芸士 木村安子


 |
伝統工芸士、初代一秀を父に持ち元文年間から受け継がれてきた【江戸木目込人形】の伝統を学ぶ。 その古典美に現代感覚を織り込みながら、洗練された上品さを漂わせ優雅な作品を次々に発表し高い評価を得ている。 平成12年に通商産業大臣指定の伝統工芸士平成26年に東京都伝統工芸士に認定される。 |
伝統工芸士 望月龍翠


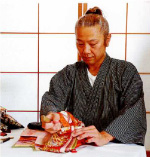 |
1964年、雛人形の産地として江戸時代からの歴史を持つ町、静岡市に生まれる。高校卒業後、老舗人形問屋にて雛人形作りを学び、のちに雛人形工房「京雛」にて雛人形士である父・幸彦に師事し、人形の制作にあたる。 |
| 2003年経済産業大臣より指定を受けている伝統的工芸品の伝統工芸士として認定される。 |
望月紀彦


 |
1970年 静岡市に生まれる。
大学卒業後、印刷関連の企業に入社しグラデーションなどの色合いについて学ぶ 1997年 先代(株)京雛に入社し雛人形衣装着製作の技術を学ぶ |
| 2010年 雛工房(株)三世を設立しオリジナル製品の製作に取り組んでいる。 雛工房(株)三世 望月紀彦作のお雛様はお殿様の袖口、お雛様の内袖かさねのラインをきれいに仕上げ、造形のバランスにこだわり製作しております。 |
清鳳


 |
昭和48年愛知県生まれ。祖父の代よりの人形作家の家系に生まれる。 父・初代清鳳に師事し、人形製作の道を歩み始める。独自の技術を駆使した人形は高く評価されています。 |
藤真(二代目 穂洲)


 |
昭和47年 節句人形職人の長男としてうまれる。 幼い頃より伝統工芸・手仕事を見て育つ。 高校卒業後、雛職人工房で修業。 修行後、東海道五十三次の藤川宿内にお雛さま工房を構える。 |
|
平成21~平成28年 中部人形節句コンクールにおいて各賞受賞。 平成27年 郷土伝統工芸品優秀技術者表彰 平成28年 名古屋伝統産業協会伝統産業優秀技術者表彰 自社工房以外での雛人形製作技術を取得した数少ない職人である。 お子様の幸せを願い全てにおいて妥協を許さず、伝統のつくりを守りながら、新しい風を取り入れた作品を制作している。 作品は主に、古来より伝わる吉祥柄(縁起の良い文様)格式の高い文様を着せ付けている。 派手ではないが、華やかさがある。世代を超えた思いをつたえる人形師として精進している。 |
|